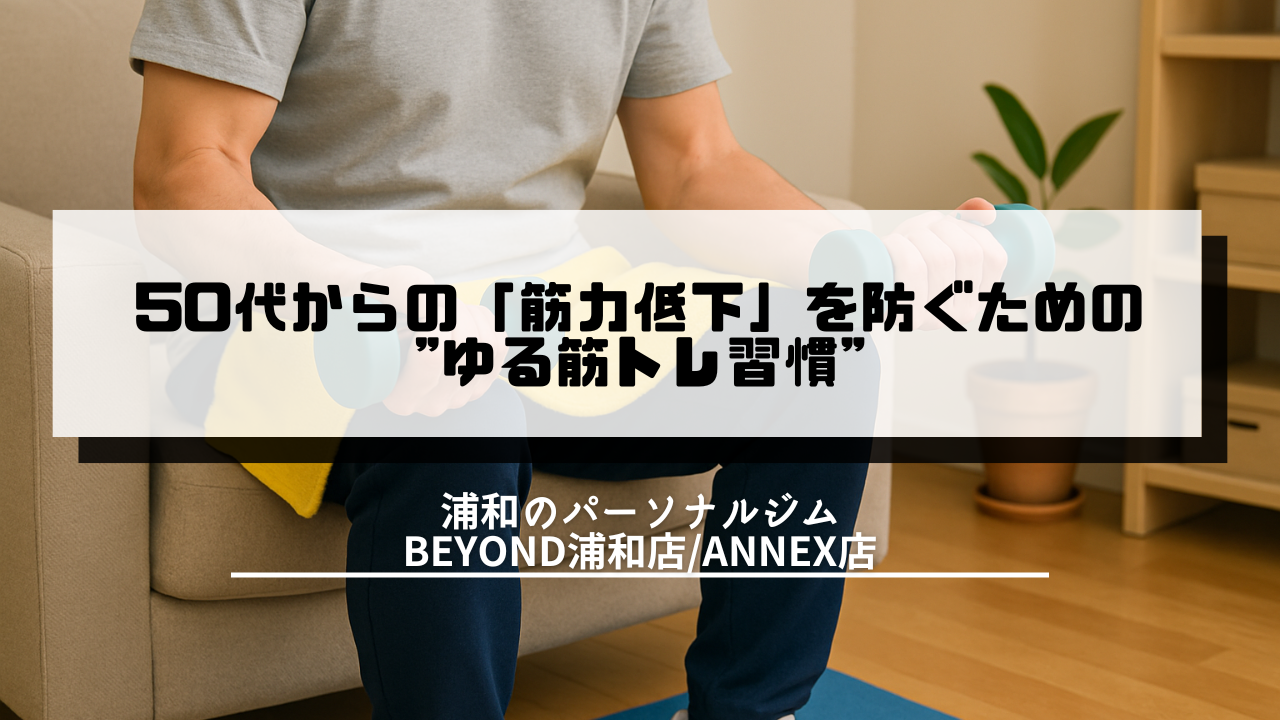みなさんこんにちは!
埼玉県の浦和にあるパーソナルジム BEYOND 浦和店 店長の宮川と申します!
筆者が勤めるパーソナルジムでは、トレーニングや食事習慣の改善を通して皆様の悩み解消や目標達成に向けたアプローチを行っています。
「最近、階段の上り下りがつらくなった」「重いものが持ちにくくなった」「つまずきやすくなった」
もしあなたが50代を迎え、このような体の変化を感じているのなら、それは加齢による「筋力低下」のサインかもしれません。
30代を過ぎると、私たちの筋肉量は年間約1%ずつ減少すると言われています。
特に50代以降は、その減少スピードが加速し、日常生活に様々な影響を及ぼし始めます。
この現象は「サルコペニア」と呼ばれ、放置すると転倒や骨折のリスクを高め、将来の健康寿命を縮める原因にもなりかねません。
しかし、「もう歳だから仕方ない」と諦めるのは早すぎます。
実は、50代からでも適切な方法で筋力トレーニングを行えば、筋肉量の減少を食い止め、むしろ増やすことも可能であることが、多くの研究で示されています。
大切なのは、無理なく継続できる「ゆる筋トレ習慣」を見つけることです。
この記事では、50代からの筋力低下のメカニズムと、それがもたらす影響について深く掘り下げます。
そして、専門家の知見に基づいた「ゆる筋トレ習慣」の具体的な方法、その効果、そして継続するためのヒントを詳しく解説します。
激しい運動は不要です。
あなたのライフスタイルに合わせた「ゆる筋トレ」で、いつまでも若々しく、活動的な毎日を送りませんか?
さあ、今日から「筋力貯金」を始めて、健康寿命を延ばしましょう。
この記事をご覧いただいている方へ。
この記事をご覧いただいている皆さまは、健康面に気を使い、食生活や運動習慣の見直し、フィットネスジムに通われている。もしくは、入会等をご検討されている健康意識の高い方々ではないでしょうか?
実際に、厚生労働省が、健康づくりのための身体活動基準・指針を作成し、生活習慣病予防のための運動を推進しています。
また、日本政策金融公庫が発表した消費者動向調査(令和3年7月)では、運動面や食に関する志向で、“健康志向”の方が多く年々と増加しています。
より皆様が、健康的で充実した人生を歩めるよう、誠意を込めて記事を執筆いたしましたので、どうか最後までご覧ください。
<その他資料>
※スポーツ庁の資料(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究(令和2年度))では、コロナ終息後のパーソナルトレーニングジムの利用者数は急増中。
※経済産業省の『特定サービス産業動態統計速報』の結果でも、フィットネスジム並びに、パーソナルジム利用者は数多くいらっしゃいます。
【PR】BEYOND

BEYONDは全国120店舗以上を展開する、BEST GYM AWARD受賞のパーソナルジム。美ボディコンテストでの入賞者や資格をもつ、プロのパーソナルトレーナーのみが揃っております。
過度な食事制限やトレーニングなく、ライフスタイルに合わせて無理なく継続できます。
コースは大きく以下3つにわかれているため、目的に合ったトレーニングを選択可能です。
| 料金(税込) ※最小プランの場合 | 内容 | おすすめ | |
| ライフプランニングコース | 月々10,100円~ ※281,600円 | パーソナルトレーニング 食事管理 | 初心者の方向け |
| ライフプランニングコース(サプリ付き) | 月々10,600~ ※296,720円 | パーソナルトレーニング 食事管理 サプリメント | 目標がある方向け |
| 回数券コース | 月々4,800円~ ※96,800円 | パーソナルトレーニング ストレッチ | 継続したい方向け |
※当社指定の信販会社を利用した際の分割料金となります。・10回券96,800円の場合:分割回数:24回/支払い期間:24ヶ月/手数料率:年利7.96%/支払い総額:115,850円
特に回数券コースの月々4,800円~は、業界内でも最安値級で良心的です。
BEYONDが気になる方は、まず無料体験トレーニングを活用してみてください。
\今なら入会金50,000円が無料/
50代からの筋力低下:そのメカニズムと影響

50代になると、多くの人が筋力低下を実感し始めます。
この現象は単なる加齢の一環として捉えられがちですが、その背後には複数の複雑なメカニズムが隠されています。
ここでは、筋力低下がなぜ起こるのか、そしてそれが私たちの体にどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきましょう。
1. サルコペニア:加齢による筋肉量の自然な減少
「サルコペニア」とは、加齢に伴い筋肉量と筋力が進行性に減少する現象を指します。
一般的に、筋肉量は30歳頃から年間約0.5~1%のペースで減少し始め、50歳を過ぎるとその減少スピードが加速すると言われています。
特に、下半身の筋肉(太ももやお尻など)は、上半身の筋肉に比べて減少率が高い傾向にあります。
この筋肉量の減少は、以下のような要因が複合的に絡み合って起こります。
- 運動不足: 身体活動量が減少すると、筋肉への刺激が減り、筋肉の分解が進みやすくなります。
- 栄養不足: 特にタンパク質の摂取量が不足すると、筋肉の合成が滞り、筋肉量の維持が困難になります。
- ホルモンバランスの変化: 成長ホルモンや性ホルモン(テストステロン、エストロゲンなど)の分泌量が減少することも、筋肉量の減少に影響します。
- 炎症: 慢性的な炎症が筋肉の分解を促進する可能性も指摘されています。
サルコペニアが進行すると、日常生活での動作が困難になるだけでなく、転倒や骨折のリスクが増加し、最終的には要介護状態に陥る可能性が高まります。
これは、単に「足腰が弱る」というレベルを超え、健康寿命を大きく左右する重要な問題なのです。
2. 基礎代謝の低下:太りやすく痩せにくい体質へ
筋肉は、私たちが消費するエネルギーの大部分を占める「基礎代謝」に大きく関与しています。
筋肉量が減少すると、基礎代謝も低下します。
基礎代謝が低下すると、これまでと同じ食事量でも消費しきれないエネルギーが体内に蓄積されやすくなり、結果として太りやすく、痩せにくい体質へと変化します。
特に50代以降は、内臓脂肪の増加も顕著になり、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まります。
3. 姿勢の悪化と関節への負担増
筋肉は、私たちの体を支え、正しい姿勢を維持するために不可欠です。
特に、体幹(お腹や背中)や下半身の筋肉が衰えると、姿勢が悪くなり、猫背や反り腰になりやすくなります。
姿勢の悪化は、首や肩、腰などへの負担を増やし、慢性的な痛みや凝りの原因となります。
また、関節を支える筋肉が弱くなると、膝や股関節などへの負担が増加し、変形性関節症などのリスクも高まります。
4. 疲労感の増加と活動量の低下
筋肉は、体を動かす際のエネルギー効率にも影響します。
筋力が低下すると、同じ動作をするにもより多くのエネルギーが必要となり、結果として疲れやすさを感じやすくなります。
例えば、少し歩くだけで息が切れたり、家事をするだけで疲労困憊になったりすることがあります。
このような疲労感の増加は、さらに活動量を低下させ、筋力低下を加速させるという悪循環を生み出します。
5. 精神面への影響:自信の喪失と活動意欲の低下
身体的な変化は、精神面にも大きな影響を与えます。
以前は簡単にできていたことができなくなると、自信を失い、外出や人との交流を避けるようになることがあります。
活動量の低下は、社会的な孤立を招き、抑うつ気分や認知機能の低下に繋がる可能性も指摘されています。
筋力低下は、単なる身体の問題に留まらず、私たちの生活の質(QOL)全体を低下させる要因となるのです。
これらのメカニズムと影響を理解することは、50代からの筋力低下対策の重要性を認識する上で不可欠です。
しかし、これらの変化は決して不可逆的なものではありません。
適切な「ゆる筋トレ習慣」を取り入れることで、これらの負の連鎖を断ち切り、健康で活動的な毎日を取り戻すことが可能です。
次のセクションでは、なぜ「ゆる筋トレ」が50代に最適なのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
50代にこそ「ゆる筋トレ」が最適な理由

「筋力低下を防ぐには筋トレが必要」と聞くと、「きつい運動は苦手」「ジムに通う時間がない」「怪我をするのが怖い」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、50代からの筋力低下対策に最適なのは、決してハードなトレーニングではありません。
むしろ、無理なく継続できる「ゆる筋トレ」こそが、この世代に最も適したアプローチなのです。
その理由を具体的に見ていきましょう。
1. 無理なく継続できるからこそ効果が出る
どんなに効果的なトレーニング方法でも、継続できなければ意味がありません。
50代になると、若い頃に比べて体力や回復力が低下し、関節や筋肉への負担も大きくなります。
ハードなトレーニングは、肉体的な疲労だけでなく、精神的な負担も大きく、三日坊主で終わってしまう可能性が高まります。
一方、「ゆる筋トレ」は、自分の体力レベルや体調に合わせて負荷を調整できるため、無理なく毎日、あるいは週に数回でも継続しやすいのが最大のメリットです。
継続こそが、筋力維持・向上への唯一の道であり、ゆる筋トレはそのための最適な手段と言えます。
2. 怪我のリスクを最小限に抑える
50代からの筋トレで最も避けたいのは、怪我です。
一度怪我をしてしまうと、運動が中断され、せっかく始めた習慣が途切れてしまうだけでなく、回復に時間がかかり、筋力低下がさらに進んでしまう恐れがあります。
ゆる筋トレは、自重や軽い負荷で行うため、関節や筋肉への負担が少なく、怪我のリスクを大幅に低減できます。
正しいフォームでゆっくりと丁寧に行うことで、筋肉を意識しやすくなり、より安全かつ効果的にトレーニングを進めることができます。
3. 日常生活の動作改善に直結
ゆる筋トレで鍛えるのは、日常生活でよく使う筋肉(抗重力筋など)が中心です。
例えば、スクワットは立ち座り、ウォーキングは歩行、プランクは姿勢維持に必要な体幹を鍛えます。
これらの運動は、特別な器具や広いスペースを必要とせず、自宅で手軽に行えるものばかりです。
日常生活の動作と直結したトレーニングを行うことで、階段の上り下り、荷物の持ち運び、立ち座りといった動作が楽になり、日々の生活の質が向上するのを実感できるでしょう。
これは、単に筋肉をつけるだけでなく、生活の「質」を高めることに繋がります。
4. 精神的な安定と自己肯定感の向上
運動は、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも大きな影響を与えます。
特に更年期を迎える50代の女性は、ホルモンバランスの変化により、気分の落ち込みやイライラを感じやすくなることがあります。
ゆる筋トレは、適度な運動によってストレスを解消し、セロトニンなどの幸福感をもたらす脳内物質の分泌を促します。
また、「運動を継続できている」「体が少しずつ変化している」という達成感は、自己肯定感を高め、精神的な安定に繋がります。
無理なく続けられるからこそ、運動が「義務」ではなく「楽しみ」となり、心身の健康をサポートしてくれるのです。
5. 基礎代謝の維持・向上と生活習慣病予防
ゆる筋トレであっても、継続的に筋肉に刺激を与えることで、筋肉量の減少を抑制し、基礎代謝の維持・向上に貢献します。
基礎代謝が維持されれば、太りにくい体質を保ちやすくなり、内臓脂肪の蓄積を防ぐことにも繋がります。
これにより、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを低減し、健康的な体を維持することができます。
ゆる筋トレは、将来の健康への投資とも言えるでしょう。
このように、「ゆる筋トレ」は、50代の身体的・精神的な特性、そしてライフスタイルを考慮した上で、最も効果的かつ継続しやすい筋力低下対策であると言えます。
次のセクションでは、具体的にどのような「ゆる筋トレ」を日常生活に取り入れれば良いのか、おすすめのメニューをご紹介します。
50代からの「ゆる筋トレ」おすすめメニュー:自宅でできる簡単エクササイズ

「ゆる筋トレ」は、特別な器具や広いスペースがなくても、自宅で手軽に始められるのが魅力です。
ここでは、50代からの筋力低下を防ぎ、日常生活の質を高めるために特に効果的な「ゆる筋トレ」メニューを厳選してご紹介します。
大切なのは、無理なく、正しいフォームで行うことです。
最初は回数が少なくても、焦らず、少しずつ増やしていきましょう。
1. 下半身を鍛える:スクワット(椅子を使ったサポート付き)
下半身の筋肉は、全身の筋肉量の約70%を占めると言われており、加齢による筋力低下が最も顕著に現れる部位です。スクワットは、太ももやお尻など、下半身全体を効率よく鍛えられる「キング・オブ・エクササイズ」です。
最初は椅子を使って行うことで、バランスを崩す心配がなく、安全に正しいフォームを習得できます。
目的: 太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)、お尻(大臀筋)の強化、立ち座り動作の改善、転倒予防。
やり方:
- 椅子の前に立ち、足を肩幅に開きます。つま先はやや外向きに。
- 背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れます。
- ゆっくりと息を吸いながら、椅子に座るように腰を下ろしていきます。膝がつま先よりも前に出すぎないように注意しましょう。
- 太ももが床と平行になるくらいまで下ろせたら、息を吐きながらゆっくりと立ち上がります。立ち上がる際も、膝を完全に伸ばしきらず、少し余裕を持たせると良いでしょう。
- この動作を10回繰り返します。慣れてきたら、15回、20回と回数を増やしたり、セット数を2~3セットに増やしたりしましょう。
ポイント:
- 膝とつま先が同じ方向を向くように意識します。
- お尻を後ろに突き出すようにすると、太ももの裏やお尻に効きやすくなります。
- 無理に深く腰を下ろす必要はありません。できる範囲でOKです。
- 椅子を使わずに、壁に手をついて行う方法もあります。
2. 体幹を鍛える:プランク(膝つき)
体幹は、体の軸となる重要な部分です。
体幹が安定すると、姿勢が良くなり、腰痛の予防・改善、そして手足の動きがスムーズになります。
プランクは、腹筋だけでなく、背中や肩、お尻など、体幹全体を効率よく鍛えられるエクササイズです。
最初は膝をついて行うことで、無理なく体幹を意識できます。
目的: 体幹の強化、姿勢改善、腰痛予防。
やり方:
- うつ伏せになり、両肘を肩の真下につき、前腕を床につけます。
- 膝を床につけたまま、お腹に力を入れて体を持ち上げ、頭から膝までが一直線になるようにキープします。
- お尻が上がりすぎたり、腰が反りすぎたりしないように注意しましょう。
- この姿勢を20秒間キープします。慣れてきたら、30秒、45秒、1分と時間を延ばしたり、セット数を2~3セットに増やしたりしましょう。
ポイント:
- お腹をへこませるように意識すると、より体幹に効きます。
- 呼吸を止めずに行いましょう。
- 慣れてきたら、膝を床から離して、つま先で体を支える通常のプランクに挑戦してみましょう。
3. 背中を鍛える:バックエクステンション(うつ伏せ)
背中の筋肉は、姿勢を保つ上で非常に重要です。
特に、猫背になりがちな50代にとって、背中の筋肉を鍛えることは、若々しい姿勢を保ち、肩こりや腰痛の予防に繋がります。
バックエクステンションは、背中全体を無理なく鍛えられるエクササイズです。
目的: 背中(脊柱起立筋、広背筋)の強化、姿勢改善、肩こり・腰痛予防。
やり方:
- うつ伏せになり、両手を頭の後ろで組むか、体の横に置きます。
- ゆっくりと息を吐きながら、背中の筋肉を意識して、上半身を床から少し持ち上げます。目線は床に向けたまま、首を反らしすぎないように注意しましょう。
- 背中の筋肉が収縮しているのを感じたら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。
- この動作を10回繰り返します。慣れてきたら、15回、20回と回数を増やしたり、セット数を2~3セットに増やしたりしましょう。
ポイント:
- 反動を使わず、ゆっくりと丁寧に行いましょう。
- 腰に痛みを感じる場合は、無理せず中止してください。
- 上半身を高く持ち上げる必要はありません。背中の筋肉が収縮しているのを感じる程度で十分です。
4. 肩・腕を鍛える:壁腕立て伏せ
腕の筋力は、日常生活で物を持ち上げたり、ドアを開けたりする際に重要です。
壁腕立て伏せは、通常の腕立て伏せよりも負荷が低く、肩や腕の筋肉を安全に鍛えることができます。
特に、二の腕のたるみが気になる方にもおすすめです。
目的: 肩(三角筋)、腕(上腕三頭筋)、胸(大胸筋)の強化、二の腕の引き締め。
やり方:
- 壁から一歩離れて立ち、肩幅よりやや広めに手をつきます。
- ゆっくりと息を吸いながら、肘を曲げて胸を壁に近づけていきます。体が一直線になるように意識しましょう。
- 胸が壁に近づいたら、息を吐きながらゆっくりと壁を押して元の位置に戻ります。
- この動作を10~15回繰り返します。慣れてきたら、20回と回数を増やしたり、セット数を2~3セットに増やしたりしましょう。
ポイント:
- 壁との距離を離すほど負荷が高まります。最初は壁に近い位置から始めましょう。
- 肘を外側に開きすぎず、やや体側に沿わせるようにすると、より効果的です。
- 肩に痛みを感じる場合は、無理せず中止してください。
5. 全身のバランスと柔軟性:片足立ち
筋力だけでなく、バランス能力も加齢とともに低下し、転倒のリスクを高めます。
片足立ちは、バランス能力を養うだけでなく、足首や股関節周りの小さな筋肉も鍛えることができます。
特別な運動というよりは、日常生活の中で意識的に取り入れられる「ゆる筋トレ」です。
目的: バランス能力の向上、転倒予防、足首・股関節の安定化。
やり方:
- 壁や椅子の近くに立ち、いつでも支えられるように準備します。
- 片足をゆっくりと床から持ち上げ、膝を軽く曲げます。
- そのままの姿勢で20~30秒間キープします。バランスが取れない場合は、壁や椅子に軽く手をついても構いません。
- 反対の足も同様に行います。
- これを左右交互に2~3セット繰り返します。
ポイント:
- 目線は一点に集中するとバランスが取りやすくなります。
- 慣れてきたら、目を閉じて挑戦してみましょう(安全な場所で)。
- 歯磨き中や料理中など、日常生活の「ながら時間」に取り入れると継続しやすくなります。
これらの「ゆる筋トレ」メニューは、自宅で手軽に始められ、50代の体に適した負荷で筋力維持・向上をサポートします。大切なのは、毎日少しずつでも継続することです。次のセクションでは、この「ゆる筋トレ習慣」を長く続けるための具体的なヒントと注意点をご紹介します。
「ゆる筋トレ習慣」を長く続けるためのヒントと注意点

せっかく始めた「ゆる筋トレ」も、途中で挫折してしまっては意味がありません。
50代からの筋力維持・向上は、一朝一夕で成し遂げられるものではなく、継続が何よりも重要です。
ここでは、運動を習慣化し、安全に長く続けるための具体的なヒントと注意点をご紹介します。
1. 小さな目標から始める:達成感が継続の鍵
「毎日30分筋トレする」「いきなり完璧なフォームで」といった高い目標を設定すると、達成できなかったときにモチベーションが低下し、挫折に繋がりやすくなります。
まずは「週に2回、スクワットを10回だけやってみる」「毎日5分だけストレッチする」など、無理なく達成できる小さな目標から始めましょう。
目標をクリアするたびに、自分を褒め、達成感を味わうことが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで、自信がつき、自然と次のステップへと進む意欲が湧いてきます。
2. 記録をつける:変化を「見える化」する
運動内容(種類、回数、時間、セット数など)や、運動後の体調の変化(疲労感、睡眠の質、体の軽さなど)を記録する習慣をつけましょう。
手帳やスマートフォンのアプリ、フィットネストラッカーなどを活用すると便利です。
記録を振り返ることで、自分の努力が「見える化」され、筋力や体調の変化を客観的に把握できます。
例えば、「スクワットの回数が増えた」「以前より疲れにくくなった」といった変化に気づくことで、モチベーションを維持しやすくなります。
また、不調を感じた際に、原因を探る手がかりにもなります。
3. 楽しむ工夫をする:運動を「義務」から「楽しみ」へ
運動を「やらなければならないもの」と捉えるのではなく、「楽しいもの」「心地よいもの」として捉えることが、継続の秘訣です。
好きな音楽を聴きながら、テレビを見ながら、あるいは家族や友人と一緒に運動するなど、自分なりの楽しみ方を見つけましょう。
新しいエクササイズに挑戦したり、運動グッズを揃えてみたりするのも良い刺激になります。
運動を通して得られる心身の変化や、達成感を味わうことで、運動が生活の一部となり、自然と継続できるようになります。
4. 専門家への相談:安全かつ効果的に
持病がある方や、運動中に痛みや体調不良を感じた場合は、無理をせずに医師や理学療法士、健康運動指導士などの専門家に相談しましょう。
自分の体質や健康状態に合わせた運動メニューや注意点について、具体的なアドバイスを受けることができます。
特に50代は、若い頃とは体の状態が異なるため、専門家のサポートを得ることで、より安全かつ効果的に筋トレに取り組むことができます。
パーソナルトレーナーの指導を受けることも、正しいフォームを習得し、モチベーションを維持する上で非常に有効です。
5. 体調の変化に合わせた調整:無理は禁物
50代は、日によって体調が変動しやすい時期でもあります。
運動計画を立てていても、体調が優れない日や、疲労感が強い日は、無理をせずに休む勇気も大切です。
無理をして運動を続けると、かえって体調を崩したり、怪我の原因になったりする可能性があります。
運動の強度や時間を調整したり、ストレッチや軽いウォーキングに切り替えたりするなど、柔軟に対応しましょう。
「今日は休む」という選択も、長期的な継続のためには必要なことです。
体と心に耳を傾け、自分を労わることも「ゆる筋トレ」の大切な一部です。
6. 日常生活に溶け込ませる:ながら運動のすすめ
「運動のための時間がない」という方もいるかもしれません。
しかし、「ゆる筋トレ」は、日常生活の中に意識的に取り入れることで、無理なく運動量を増やすことができます。
例えば、歯磨き中に片足立ちをする、テレビを見ながらスクワットをする、通勤時に一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、ちょっとした工夫で運動の機会を増やすことができます。
これらの「ながら運動」は、特別な時間を設けずに筋力維持に貢献し、運動を習慣化する第一歩となります。
これらのヒントと注意点を参考にしながら、「ゆる筋トレ習慣」をあなたのライフスタイルに取り入れてみてください。
無理なく、楽しく、そして安全に運動を継続することで、50代からの筋力低下を防ぎ、より充実した毎日を送ることができるでしょう。
まとめ:50代からの「ゆる筋トレ」で、健康寿命を延ばそう

50代からの筋力低下は、サルコペニアをはじめとする様々な身体的・精神的な不調を引き起こし、私たちの生活の質(QOL)を大きく低下させる可能性があります。
しかし、この記事でご紹介したように、決して諦める必要はありません。
無理なく継続できる「ゆる筋トレ習慣」を日常生活に取り入れることで、筋肉量の減少を食い止め、むしろ筋力を向上させ、健康寿命を延ばすことが可能です。
大切なのは、完璧を目指すのではなく、「できることから、少しずつ、楽しく続ける」ことです。
今日から、自宅で手軽にできるスクワットやプランク、バックエクステンション、壁腕立て伏せ、片足立ちといった「ゆる筋トレ」を始めてみませんか?小さな一歩が、あなたの未来の健康と活力を大きく変えるはずです。
筋力は、私たちの生活の土台です。
この土台をしっかりと築き、いつまでも自分の足で歩き、好きなことを楽しめる、そんな充実した50代、60代、そしてその先を送りましょう。
あなたの「ゆる筋トレ習慣」が、健康で輝かしい未来への扉を開くことを願っています。
参考文献
- 厚生労働省. 「健康づくりのための身体活動基準・指針」. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html
- スポーツ庁. 「国民の健康・体力に関する世論調査」.
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/sports/1402342.htm - 国立健康・栄養研究所. 「健康日本21(第二次 )の推進に関する参考資料」. https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/